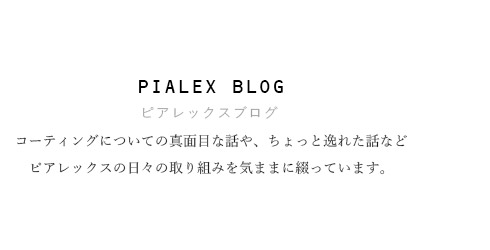2液型塗料について
あの、ここだけの内緒の話ですが・・・
他人には「2液型塗料の主剤/硬化剤配合はハカリを使って厳格に!」
と言っている私自身はたいてい目分量です。
某塗料メーカーのサラリーマン時代に
「どこまで主剤/硬化剤比率をずらせたら悪影響が出るか」という遊び実験をしたことがあるので・・・
平和でヒマな会社でしたねぇ。
ウレタン硬化性塗料だと主剤のOH基と硬化剤のイソシアネートNCO基の数を1:1にするのが基本ですが
最大20%ずらしても耐候性を含めて性能に大した影響はありませんでしたね。
(防水材料は粘弾性をつけるためにそもそもNCOの比率が下限なので注意してください!)
エポキシ系塗料に至っては主剤のグリシジル基と硬化剤の活性水素の比率を最大50%ずらしてもOKでした。
こんなことを述べて「だから2液型塗料の配合なんて目分量でいいんだ!」と唱えるのが今回の主旨ではなく
「計量作業って煩わしいからみんな嫌なんだよ、なんとか1液型にできないものか。」と提案したいのです。
メーカーの技術者は計量に電子天秤を使うので2kgと500gの混合なんてものも直ぐにできますが、
たとえば現場で上皿天秤を使った場合445gの風袋の缶に2kgの主剤を入れると2,445g・・・
とそれに500g足すと2,945g・・・
と・・・ってこれをいつも正確にできる自信のあるヒトは何人いることか。

「それならもう巷には1液ウレタンとか1液シリコンとかあるわな!」とおっしゃる方もいますが、
あれは、主剤の分子量を大きくして「乾いたように見せている」だけで
架橋硬化反応を起こす塗料ではないので性能はかなり落ちますよ!!
そこで提案なのですが!初めから主剤と硬化剤を混ぜておけばどうでしょう。
もちろんそんなことをすれば24時間以内に硬化してしまいます・・・常温ではね。
イソシアネートもエポキシも5℃以下の低温では反応が進行しないのでこれを逆手に取ればいいのです。
つまり主剤と硬化剤を混ぜた状態の塗料を使う直前まで5℃以下に冷やしておくと
理論上は「計量しないでいい(というか計量が終わった後の)2液性塗料」ができあがります。
あの頃は私も好奇心と探究心の固まりだったので
「ドライアイスポケットのついた1斗缶用ジャケット」なんかも試作してたんですが・・・
20年前です。特許は公知になっていますのでご興味の方はご自由にお使い下さい